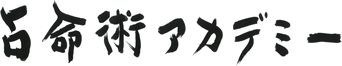七十二候
今年は去年の二十四節気に七十二候も取り入れていきたいと思います。
七十二候とは、二十四節気をさらに3つの候(初候・次候・末候)に細分割しています。
季節の移り変わり・気象の変化・動物や植物の成長などに例えて表現されたものですが、一候が「約五日」程度と短いので地域やその年の気候の違いなどで現実と合わないことが多くあるようです。
また本来中国で考案された「季節」を表す短文なので「野鶏入水蜃」・・・キジが海に入って大ハマグリになるというような実際にはあり得ない事柄も含まれています。
また二十四節気と違い七十二候の名称は何度か変更されているようです。
日本でも江戸時代に入ってきた折に、日本の風土に合うように作成されました。
現在使用しているものは、明治時代(明治七年)に作成された「略本暦」が主流となっています。